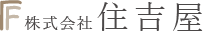みそが初めて作られたのはいつ頃なのか、その起源ははっきりしていないようですが、奈良時代になる少し前の文献には登場しているため、わが国ではかなり古くから食べられていたものと思われます。一方、味噌汁は「御御御付け(おみおつけ)」とも呼ばれていますが、「御」を3つも重ねて使うのは味噌汁だけで、毎日の食卓の中でどれだけ大切にされてきたのかが良くわかる表現になっています。鎌倉時代の武士の文化から生まれたと言われている「一汁一菜」は、ご飯に「汁」と「菜」だけという質素な食事を思い浮かべがちですが、この場合の「汁」は具沢山の味噌汁であり、副菜(=おかず)を意味する「菜」は干し魚なども供されていたため、比較的バランスの取れた食事であったのではないかと言われています。また、「みそ汁一杯三里の力」ということわざもあります。これは1杯のみそ汁を飲めば3里を歩いても疲れないという意味が込められています。実際、みそには様々な栄養効果が認められており、その主なものとしては①ガンのリスクを下げる②生活習慣病を予防する③老化を防止するなどがあります。①については、例えば「みそ汁の摂取が多いほど乳がんになりにくい」という厚労省の調査成果があるなど、色々なガンに対する効果が科学的に裏付けされてきています。②は血圧を下げる効果や、糖尿病や骨粗鬆症を改善するなどの効果につながるといった研究結果が示されています。③は発酵食品ならではの抗酸化作用によって老化を制御し、脳卒中の発症を抑えるなどの報告がなされています。その他にも身体に様々なメリットがあるみそ汁、食生活の中に上手く取り入れていきたいものです。