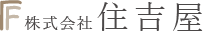つみれは、魚のすり身をつまみとりながら鍋に入れるため、「つみ入れ」から「つみれ」になったと言われています。イワシやサバ、アジなどの魚を原料としたものが多く、それらをミンチ状にすることで、青魚特有の旨みが引き出されます。これら青魚にはDHAやEPAといった不飽和脂肪酸を多く含むことはよく知られていますが、特にDHAは子供の脳や神経の成長に有効な成分だと言われています。魚の脂に含まれているDHAは、火を通すなど調理によって失われていきますが、汁ものにして汁ごと飲めば、栄養成分を逃すことなく摂取できます。春は、脂の乗った青魚がたくさん獲れる季節。この時期に食べるつみれ汁は、そういった意味でも、身体に良いおかずと言えます。つみれ汁は、地方によってつみれに使う材料に特徴があり、地の魚を使ったつみれ汁を振舞われて感激したという旅人の話もよく聞きます。北海道や東北(宮城県)では、サンマのつみれ汁が有名です。イワシやサバなどと違い、昨夏から秋にかけて旬となるサンマは、秋野菜と一緒に食べる郷土料理です。一方、山陰や九州地方では「アゴ」と呼ばれるトビウオを才材料にしたつみれ汁が食べられています。アゴの名前の由来は、「アゴが外れるほどおいしい魚」から来ているという俗説もあるようですが、高級だしの材料としても知られているため、説得力があります。